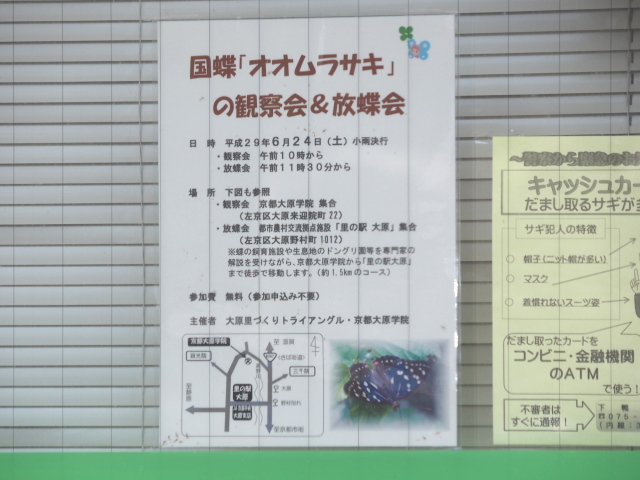2017 婥傑偖傟傾儖僶儉
僟僀僕僃僗僩斉 嘆
丂丂2017.1.3
丂柧偗傑偟偰偍傔偱偲偆偛偞偄傑偡丅
2017擭偑僗僞乕僩偟傑偟偨丅
杮擭偼僩儕擭偱偡偹丅
偦偙偱崱擭偺堦枃栚偼捁偺幨恀丒丒偭偰偄偆偺傕巹傜偟偔側偄偺偱丄
 僣僶儊僔僕儈丂2014.4.22丂嫗搒晎捲婌孲
僣僶儊僔僕儈丂2014.4.22丂嫗搒晎捲婌孲
偙偙偼柍棟傗傝丄捁偺柤慜偑榓柤偵娷傑傟傞挶偐傜堦枃慖傫偱傒傑偟偨丅
偪側傒偵巹偑崙撪偱弌夛偭偨挶偱丄捁偺柤慜偑晅偄偨傕偺偼丄偙偺乽僣僶儊乿偑俉庬丄乽僇儔僗乿偑俈庬丄乽僋僕儍僋乿偑侾庬偱寁16庬偱偟偨丅
偝傜偵丄巹偼僸儅恖偱偡偐傜丄偮偄偱偵怓乆悢偊偰傒傑偟偨丅
丂捁埲奜偺摦暔偑柤慜偵晅偄偨傕偺偼丄摉慠乽挶乿偑懡偄偲巚偄傑偟偨偑丄寢壥偼乽僔僕儈乿偑76庬丄乽挶乿偼50庬丅
師偄偱乽僸儑僂乿偑18庬丄乽幹乿偑11庬丄乽屨丒僞僀儅僀乿偑奺侾庬偱偟偨丅
懕偄偰偼怓偱偡丅
丂怓傪昞偡扨岅偑柤慜偵晅偄偨傕偺偼丄乭敀偑懡偄偐側丒丒乭偲巚偄傑偟偨偑丄偙傟偼嬐嵎偱乽墿乿偑僩僢僾偱偟偨丅
乽墿乿31庬丄乽敀乿30庬丄乽崟乿24庬丄乽愒乮峠乯乿20庬丄乽椢乿14庬丄乽椱棡丒拑乿奺10庬丄乽巼乿俋庬丄乽嬧乿俈庬丄乽惵乿俆庬丄乽愺擪乿係庬丄乽姃丒敄怓乿奺俁庬丄乽悈怓丒嬥丒揝怓乿奺侾庬丅
乽墿乿偼丄堄奜偲乭僉儅僟儔乭偱悢傪壱偓傑偟偨丅
丂偟偐偟側偑傜崱屻丄僩僢僾憟偄偼丄僔儘僠儑僂椶偺柪挶偱乽敀乿偑堦婥偵媡揮壜擻丅
傑偨丄乽椱棡乿偼儖儕僔僕儈宯丄儖儕儅僟儔宯偑憹壛偡傟偽丄妝乆弴埵傪忋偘傞偱偟傚偆丅
丂怴擭憗乆偔傜偄丄柌偼戝偒偔帩偪偨偄傕傫偱偡丅 偱偼崱擭傕傛傠偟偔偍婅偄偟傑偡丅
丂丂2017.1.27
丂姦偄擔偑懕偄偰偄傑偡丅
崱擭偺弶嶣傝偼傑偩傑偩愭偵側傝偦偆偱偡丅
丂偝偰丄尰嵼 乽庬椶暿傾儖僶儉乿 傪嵞曇廤偟偰偄傑偡偑丄夁嫀偺戝検偺嵼屔幨恀偐傜僱僞傪扵偟偰偄傞偲丄乽 僸儑僂儌儞僠儑僂乿 偺僗僩僢僋偐傜夰偐偟偄堦枃偑栚偵巭傑傝傑偟偨丅
乭偙傟丄崟斄偑敪払偟偰傞偟嵹偣傛偐側丒丒堦墳丄僐僸儑僂儌儞偲嵞敾暿偟偲偙 乭
偟偐偟丄娞怱偺慜憷侾b幒偺斄栦偑堦偮懌傝傑偣傫丅
 僂儔僊儞僗僕僸儑僂儌儞乮亯乯丂2001.8.5丂挿栰導栘慮孲
僂儔僊儞僗僕僸儑僂儌儞乮亯乯丂2001.8.5丂挿栰導栘慮孲
丂偦傟偵偟偰傕丄僂儔僊儞僗僕偲娫堘偆偐丠 丒丒 偙傟偑摉帪偺巹偺椡検偱偡側丅
丂巚偊偽丄偙偺幨恀傪嶣偭偨偺偼弶傔偰栘慮偺奐揷崅尨傪朘傟偨擔偱偟偨丅
峸擖偟偨偽偐傝偺怴幵偱栭拞偵弌敪丅
憗挬偵摓拝偟丄僼傿儖儉僇儊儔傪庤偵儚僋儚僋偟側偑傜偺扵嶕偱偟偨丅
寢嬊偙偺擔偼弶懳柺偺挶偑俆庬椶傕憹壛偟丄偦偺拞偵偼丄嶣塭帪偵偼敾暿偱偒側偐偭偨傕偺偺婓彮庬僠儍儅僟儔僙僙儕傕娷傑傟偰偄傑偟偨丅
丂崱怳傝曉傞偲丄摉帪偼挶偵娭偡傞尒幆偼愺偐偭偨偱偡偑丄偦傟側傝偵偲偰傕妝偟偄帪婜偩偭偨傛偆側婥偑偟傑偡丅
丂丂2017.2.22
丂姦偝偑彮偟偯偮娚傫偱偒偰丄婥帩偪傕僜儚僜儚偟偰偔傞崱擔偙偺崰偱偡丅
偟偐偟丄揤婥梊曬傪尒偰傕丄俀寧拞偵挶傪尒傞偺偼偪傚偭偲尩偟偦偆偱偡丅
丂偲偄偆傢偗偱崱夞傕挶僱僞偼嶣傟偦偆偵側偔丄儈儔乕儗僗傪帩偭偰偐傜弌斣偑側偔側偭偰偄傞僆儕儞僷僗E-3傪僂僅乕僉儞僌偵楢傟偰偄偒傑偟偨丅

丂抧尦丄栘捗愳偺棳傟嫶偱偡丅 媣乆偵懳娸偺敧敠巗傑偱曕偄偰搉傝傑偟偨丅
嬤擭丄憹悈偵傛偭偰嫶偑偨偰懕偗偵棳偝傟偰偟傑偄傑偟偨偑丄側傫偲偐嵞寶偝傟偰椙偐偭偨偱偡丅
偙偙偼巕嫙偺崰偺怓乆側巚偄弌偑媗傑偭偨応強側偺偱偡丅
丂偦偆偄偊偽巹偑巕嫙偺崰偼丄嫶媟偡傋偰偑栘偱巟偊傜傟偰偄偨偲巚偄傑偡偑丄崱夞偼嫶媟偦傟偧傟偺椉抂埲奜偼揝惢偵側偭偰偍傝傑偟偨丅
彮偟晽忣偼幐傢傟偨傛偆側婥偑偟傑偡偑丄帪戙偺棳傟偵傕棳偝傟偮偮偁傞棳傟嫶偲偄偭偨偲偙傠偱偟傚偆偐丅
丂傑偀丄巇曽側偄偱偟傚偆偹丅
嵞寶偺偨傃偵惻嬥傑偱偳傫偳傫棳傟偰偄偭偰偟傑偆傢偗偱偡偐傜丒丒

丂
岦偙偆偵尒偊偰偄傞忛梲巗乣媣屼嶳挰懁偺掔杊偼梒彮婜偐傜挶傪捛偭偰偄傞抧尦僼傿乕儖僪偱偡丅
帪婜偵側傞偲晅嬤傪儂僜僆僠儑僂偑旘傫偱偄傑偡偺偱丄挶壆偱慱偄偵棃傜傟偨曽偵偼丄尒妎偊偺偁傞晽宨偐傕偟傟傑偣傫丅
嵍偵尒偊偰偄傞偺偼斾塨嶳偱偡丅
丂嫶偐傜壨尨傊崀傝傞偲丄帪戙寑偺嶣塭傪挱傔偰偄偨偙偲傗丄桍偺栘偱僎儞僕乮僋儚僈僞儉僔乯傪尒偮偗偨偙偲丄
扴擟偺愭惗偑嫶偐傜掁傝巺傪悅傟偰偄傞巔丄搚梛偺屵屻偵僋儔僗偱僶乕儀僉儏乕傪偟偨偙偲丄扤偐偺僒儞僟儖偑曅偭傐愳傊棳偝傟偰戝憶偓偟偨偙偲側偳偑夰偐偟偔巚偄弌偝傟傑偟偨丅
丂偦偟偰丄壨尨偵棊偪偰偄偨姶偠偺偄偄棳栘傪堦偮丄廍偭偰婣偭偰偒傑偟偨丅
挶偑偄側偄帪婜偺妝偟傒傪堦偮丄尒偮偗傜傟偨偐傕偟傟傑偣傫丅
丂埲忋丄崱夞偼抧尦晽宨偺徯夘傒偨偄側婰帠偵側傝傑偟偨丅
丂丂2017.3.29
丂偦偆偄偊偽嶐擭偼丄乭亰傪扵偣両乭偲偄偆僥乕儅偱挶傪捛偄偐偗傑偟偨偑丄崱擭偼摿偵峫偊偰偄傑偣傫丅
偲傝偁偊偢丄嶐擭偵懕偄偰亯亰扨埵偱偺枹嶣塭庬偲丄偦傟偵壛偊偰憷昞傪嶣偭偰偍偒偨偄庬椶傪儃僠儃僠慱偭偰偄偔梊掕偱偡丅
傕偪傠傫丄塱墦偺僥乕儅丄乭 怴婯嶣塭庬偺捛壛 乭 偼忬嫷偵墳偠偰嵟桪愭偱偡丅
丂偦傫側傢偗偱丄傑偩僔乕僘儞偼巒傑偭偨偽偐傝偱偡偑丄嬤強偱僞乕僎僢僩傪扵偡偙偲偵偟傑偟偨丅
慱偄偼墇搤柧偗傾僇僞僥僴亯丄儖儕僞僥僴亯丒亰偱偡丅
 儖儕僞僥僴丂丂2017.3.29丂嫗搒晎捲婌孲
儖儕僞僥僴丂丂2017.3.29丂嫗搒晎捲婌孲
丂崱夞丄側傫偲偐尒偮偗偰嶣塭偵惉岟偟偨傕偺偺丄曔妉偱偒偢丄惈暿偼暘偐傜偢偠傑偄丅
嶣塭偑儊僀儞偵側偭偰偐傜丄嵦傞偺偑壓庤偵側偭偰偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅
彫妛惗偺崰丄壗搙傕昗杮偵偟偨婰壇偑偁傝傑偡偑丄偳偆傗偭偰嵦偭偰偨傫傗傠丒丒丒
丂丂2017.4.21
丂嬤強偺掔杊偵傕傛偆傗偔弔偺挶偑弌懙偄傑偟偨丅
嶐擭傛傝傕10擔埲忋抶傟偰偄傞姶偠偱偡丅
怴慛側傾僎僴椶偺亯俁庬傪宖嵹偟傑偡丅
 僕儍僐僂傾僎僴丂乮亯乯丂丂2017.4.20丂嫗搒晎忛梲巗
僕儍僐僂傾僎僴丂乮亯乯丂丂2017.4.20丂嫗搒晎忛梲巗
丂崟偄挶傪旤偟偔尒偊傞傛偆偵嶣傞偺偼擄偟偄偱偡偑丄挶偵業弌傪崌傢偣偰嶣偭偰傒傑偟偨丅
 僉傾僎僴丂乮亯乯丂丂2017.4.21丂嫗搒晎忛梲巗
僉傾僎僴丂乮亯乯丂丂2017.4.21丂嫗搒晎忛梲巗
丂梒彮婜偐傜丄巹偵偲偭偰偼 乭掔杊偺墹幰乭 揑側懚嵼偺挶偱偡丅
弔宆偼傗傗彫宆偱偡偑丄旤偟偝偱偼偙偺帪婜偺屄懱偑堦斣偩偲巚偄傑偡丅
 儂僜僆僠儑僂丂乮亯乯丂丂2017.4.21丂嫗搒晎忛梲巗
儂僜僆僠儑僂丂乮亯乯丂丂2017.4.21丂嫗搒晎忛梲巗
丂嬤擭丄僕儍僐僂傾僎僴偺悢偑嵞傃憹偊偰偒偨側偀偲巚偆堦曽丄杮庬偼傗傗尭偭偰偄傞傛偆偵姶偠傜傟傑偡丅
偟偐偟丄偙偺掔杊偱弶傔偰杮庬傪嶣塭偟偰偐傜憗25擭丅
怴嶲偺挶偲偼偄偊丄巐敿悽婭埲忋傕旘傃懕偗偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅
丂巹傕偦傟偩偗嵨傪偲偭偨偲偄偆偙偲偱偡側丒丒丒
丂丂2017.5.5
丂楢媥慜偐傜婥壏偺崅偄擔偑懡偔丄挶偺敪惗傕弔愭偺抶傟傪庢傝栠偟偮偮偁傞傛偆偱偡丅
慜夞偺峏怴屻傕丄憡曄傢傜偢嬤椬傪僂儘僂儘偟偰偄傑偡偑丄僩儔僼僔僕儈側傫偐偼椺擭傛傝傕憗偄傛偆側婥偑丒丒丅
側傫偩偐崱擭偺弔偼抁偐偐偭偨傛偆側婥偑偟傑偡丅
 僩儔僼僔僕儈丂乮亯乯丂丂2017.4.27丂嫗搒晎捲婌孲
僩儔僼僔僕儈丂乮亯乯丂丂2017.4.27丂嫗搒晎捲婌孲
丂弡偺挶偲偟偰丄偲傝偁偊偢弔宆偺僩儔僼僔僕儈傪堦枃丅
杮庬偺弔宆偼崙嶻挶偺拞偱傕 乭憷棤偑塮偊傞挶乭 偺僩僢僾僋儔僗偵擖傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅
捒偟偄挶偱偼偁傝傑偣傫偑丄偙偺帪婜丄摗丄嶳悂丄嬎偺壴側偳偲偲傕偵婫愡傪姶偠偝偣偰偔傟傞懚嵼偱偡丅
丂丂2017.5.20
丂僷僢偲偟偨挶偺幨恀偑偁傝傑偣傫丅
偩偐傜偲偄偭偰柍棟偵嵹偣傞傎偳偺僱僞偱傕側偄偺偱偡偑丒丒

丂尰嵼偺垽幵偺憤憱峴嫍棧偼243687km丅
2001擭丄奺抧傊挶嶣傝墦惇偵弌偐偗傞偨傔乮仌斵彈嶌偭偰僪儔僀僽偡傞偧両偺偨傔 乯偵峸擖偟偨怴幵傕丄偙偺俇寧偱17擭栚偵撍擖偟傑偡丅
14擭栚偐傜壛嶼偝傟偰偄傞惻傕僶僇偵側傝傑偣傫偑丄傑偩栤戣側偔憱偭偰偄傞偺偱崱壞偺墦惇傕偍悽榖偵側傞梊掕偱偡丅
丂偟偐偟丄偁偲偳傟偔傜偄憱偭偰偔傟傞傫傗傠丒丒丒
丂傕偟30枩僉儘傪寎偊偨傜僔儍儞僷儞偱傕妡偗偰傗傝傑偟傚偆偐偹丅
傑偭偡偖憱傜側偔側偭偨傝偟偰乮徫
丂傑偀丄幵偑僿僞傟偽丄妶摦僗僞僀儖傕戝偒偔曄傢傞偐傕偟傟傑偣傫丅
丂丂2017.6.23
丂愭擔丄嫗搒巗撪偺朸僐儞價僯挀幵応偱僷儞傪杍挘偭偰偄傞偲丄栚偺慜偵挘傝巻偑偁傞偺偵婥晅偒傑偟偨丅
傢偞傢偞幵拞偐傜僔儍僢僞乕傪愗傞傎偳偺僱僞偱偼側偄偱偡偑丄乽曻挶乿偵偼偮偄斀墳偟偰偟傑偄傑偡丅
偒偭偲堦斒揑偵偼旝徫傑偟偄僀儀儞僩偱偁偭偰丄乽曻挶乿偵夰媈怱傪書偔巹偼傂偹偔傟幰側偺偱偟傚偆丅
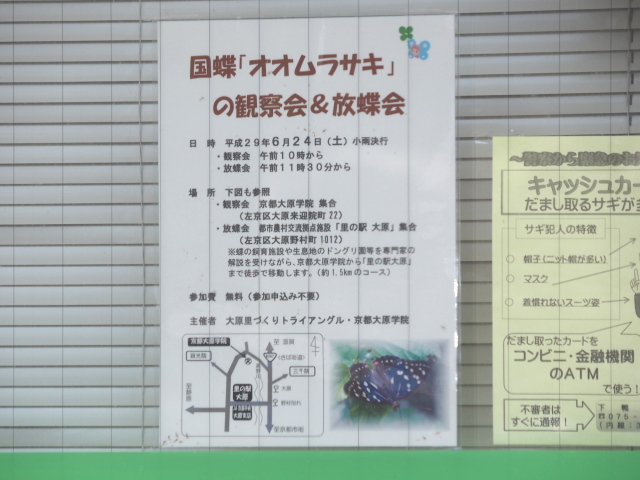
丂偝偰丄僆僆儉儔僒僉傕嶣傝懌傝側偄挶偺堦偮偱偡偑丄崱夞偺僱僞偼僛僼傿儖僗偱偡丅
巹偑埲慜偐傜朘傟偰偄傞娭惣丄壀嶳偺僛僼偼丄椺擭傛傝傗傗抶傟偰偄傞姶偠偑偟傑偡丅
傕偟偔偼丄嬤擭丄敪惗偺憗偄擭偑懡偔丄巹偺婎弨偑偢傟偰偟傑偭偰偄傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅
偲丄愭偵尵偄栿傪偟偰偍偒傑偡乮徫丅
 僋儘儈僪儕僔僕儈 乮亯乯丂丂2017.6.20丂壀嶳導怴尒巗
僋儘儈僪儕僔僕儈 乮亯乯丂丂2017.6.20丂壀嶳導怴尒巗
丂慱偭偰偄偨偺偼亰偺憷昞偱偟偨丅
埲慜丄杮庬傪嶣塭偟偨僫儔僈僔儚偺懡偄怷偱偼僸儘僆價偽偐傝旘傃弌偡偺偱丄巇曽側偔僋僰僊椦偦偺傕偺傪敿擔偐偗偰扵嶕丅
偦偟偰弌偰偒偨偺偼僺僇僺僇偺亯丅
偡偱偵亰傕弌偰偄傞偲峫偊偰偄偨偺偼撉傒堘偄偩偭偨傛偆偱偡丅
棃廡丄嵞朘偟傑偟傚偆丅
 儈僪儕僔僕儈 乮亯乯丂丂2017.6.23丂帬夑導戝捗巗
儈僪儕僔僕儈 乮亯乯丂丂2017.6.23丂帬夑導戝捗巗
丂僞乕僎僢僩偼枹嶣塭偺AB宆亰丅
乽傑偩偠傖両乿 偲桞堦尰傟偨亯偵捛偄曉偝傟傑偟偨丅
丂丂2017.6.30
丂傛偆傗偔攡塉傜偟偄揤婥偵側偭偰偒傑偟偨丅
僛僼傿儖僗嶣塭偼塉傪偳偆棙梡偡傞偐偱惉壥傕曄傢偭偰偒傑偡丅
峳揤偺梻挬丄挶偑壓傊崀傝偰偄偨傝丄塉偺巭傒娫偵堄奜偲旤偟偄奐憷僔乕儞偑嶣傟偨傝偡傞傕偺偱偡丅
丂岲揤偐傜峳揤偱惉壥傕岲揮偟偰梸偟偄偲偙傠偱偡丅
 僋儘儈僪儕僔僕儈 乮亰乯丂丂2017.6.27丂壀嶳導怴尒巗
僋儘儈僪儕僔僕儈 乮亰乯丂丂2017.6.27丂壀嶳導怴尒巗
丂亯傪嶣塭偟偰偐傜堦廡娫宱偪丄崱搙偼怴慛側亰偑尒傜傟傑偟偨丅
慜夞丄傗偼傝亰傪慱偆偵偼帪婜偑彮偟憗偐偭偨偺偱偟傚偆丅
丂僛僼偺僞乕僎僢僩偱巆偭偰偄傞偺偼傎偲傫偳偑亰偺憷昞偱偡偑丄偙傟偱堦偮僋儕傾偱偡丅
 儈僪儕僔僕儈 乮亰乯丂丂2017.6.30丂帬夑導戝捗巗
儈僪儕僔僕儈 乮亰乯丂丂2017.6.30丂帬夑導戝捗巗
丂偙偪傜傕亯傪嶣塭偟偰偐傜堦廡娫宱偪丄怴慛側亰偑弌偰偒傑偟偨丅
慱偭偰偄偨AB宆偱偡丅
偙偺屻丄偒傟偄側梩偭傁偵桿摫偟傛偆偲彮偟嬃偐偣傞偲丄偁偀丒丒墦偔傊丒丒乮徫